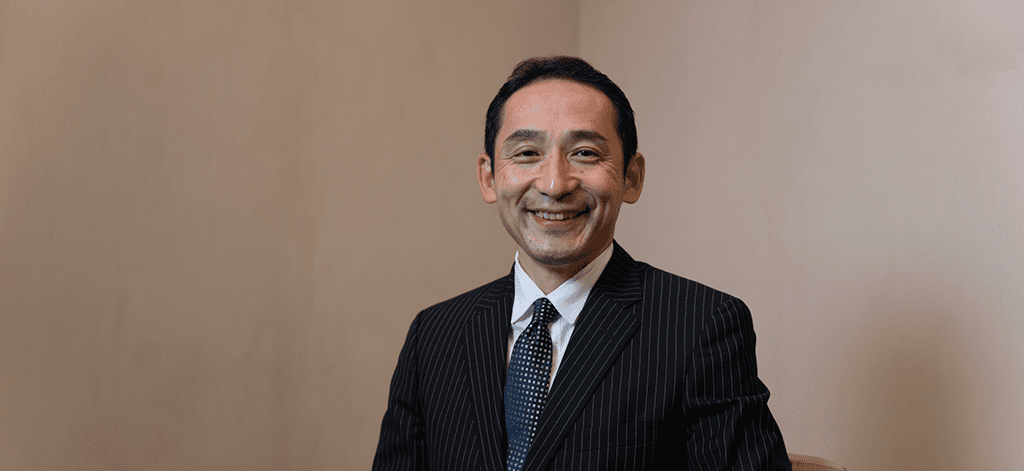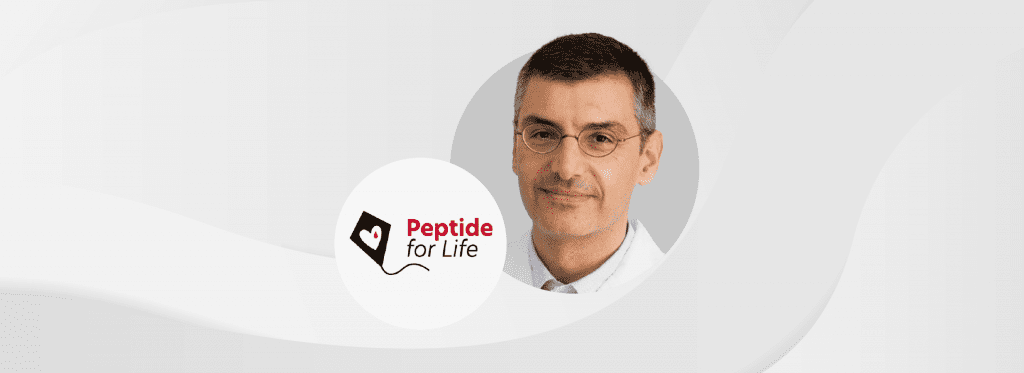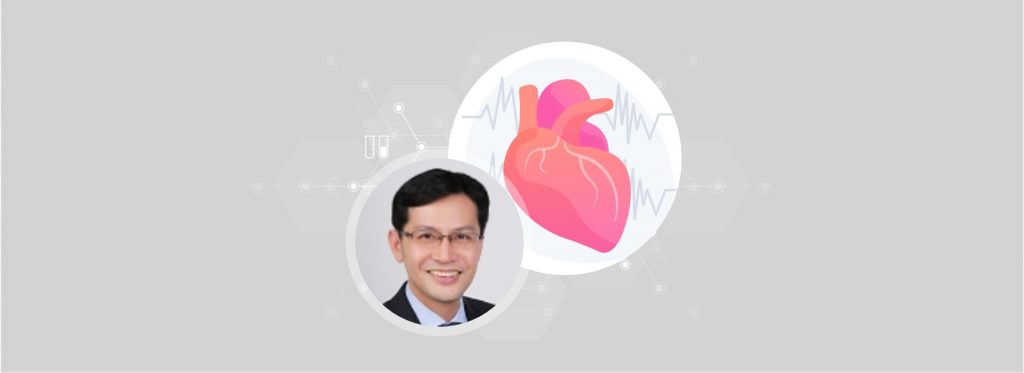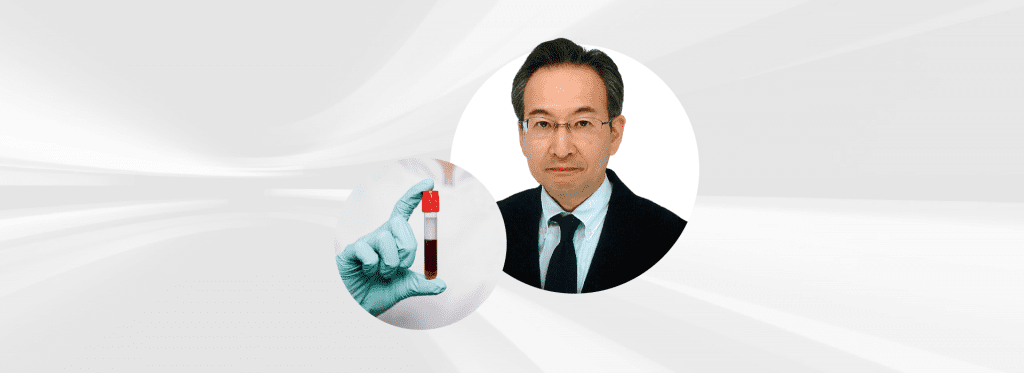STRONG-HF Japan試験: 急性心不全患者におけるGDMTの漸増
お話しいただいた内容:
はじめに
埼玉医科大学総合医療センター心臓内科の石原嗣郎でございます。
急性心不全で入院した患者におけるガイドラインに準拠した薬物療法(GDMT)の漸増に関する、STRONG-HF-JAPAN試験の目的は何ですか?
しかしながら、心不全患者のその多さばかりが問題ではありません。
心不全患者の予後が非常に悪く、癌と匹敵するほど不良であることも喫緊の課題の一つであると言えます。
また、各治療薬の投与量と予後の関係についても報告があります。ACE阻害薬、ARBおよびβブロッカーをガイドラインに定められた推奨用量の100%に達したHFrEF患者さんは、50%未満の患者さんと比較して予後の改善が得られたという報告もされました。
しかしながら、日本を含むアジアを中心としたHFrEF患者さんに対する薬剤の投与量を調査した報告によると、ACE阻害薬、ARB、βブロッカー、MRAはそれぞれ77%、79%、58% に投与されておりましたが、一方で、ガイドラインに推奨される最大用量を処方された患者さんの割合については、それぞれ17%、13%、29% に過ぎなかったと報告されています。
一方で、2021年のESCの心不全の治療ガイドラインでは、急性心不全で入院となった患者さんを退院後早期にフォローアップをし、薬剤を増量するということを推奨しております。
しかし、この推奨のエビデンスレベルは低く、フォローアップの頻度や内容及び治療薬の投与ガイダンスというのはほとんど明らかにされてこなかったということです。
このような背景のもと、急性心不全患者におけるガイダンスに基づいた迅速な薬剤の増量及び綿密なフォローアップの有効性、安全性の評価を目的としたSTRONG-HF試験が行われました。
鬱血の評価として、身体所見、心不全症状および徴候、更に腎機能、電解質異常、NT-proBNPを含む検査値を用いた多角的なフォローアップを実施することで、安全に心不全治療薬の増量を行うことができたと報告されました。**その結果、心不全治療が安全に最大用量まで達成できた患者さんが大幅に増えることにより、180日後の予後を改善する結果を示したということであります。
この報告をもとに、**2023年、ESCの心不全治療ガイドラインフォーカスアップデート版では、心不全の再入院や死亡のリスクを減少させるためには、退院前のみならず、退院後も早期に、かつ頻回に経過観察を行い、GDMTを開始し、迅速に治療薬を増量する。そういった集中的な戦略が推奨されると追記されました。**これはクラスIエビデンスレベルBというふうに評価されます。
一方で、国内においては、ガイダンスに基づいた迅速なアップタイトレーションを安全に行うかどうかについては、まだまだエビデンスが不足しているというような状況であります。
以上を踏まえ、本研究では、日本人急性心不全患者さんにおいても、ガイダンスに基づいた心不全治療薬を迅速かつ安全に増やすことができるかどうか、それを明らかにすることを検討することといたしました。
本試験で用いた漸増プロトコルの変更内容を教えてください。
STRONG-HFを日本版に修正するにあたり、欧米との違いを考慮に入れる必要がありました。**最も大きな違いは入院期間にあるのだろうというふうに思います。日本の場合、ご存じのように欧米に比較して入院期間が長いという特徴があります。しかし、それを最大限に生かすということが重要であるというふうに考えました。
STRONG-HFのプロトコールでは、退院2日前にスクリーニングを行い、強化群と通常ケア群の2つにランダム化されました。つまり、薬剤を開始された後すぐに退院したというようなプロトコールです。副作用の確認などを外来で行うプロトコールとなっていました。
STRONG-HF-JAPANにおきましては、血圧、心拍数、腎機能、電解質の推移を入院中に追うことができるわけであります。**このプロトコールで治療を行ったことがある医師は、日本にはほとんどいないという現状を考えますと、少しはその不安感を取ることができたのではないかと思います。実際に我々も血圧、心拍数を目の前で観察できましたし、その都度患者さんに症状などを確認できました。これは非常に大きなアドバンテージだったと考えています。
また、薬剤についてもSTRONG HFから大きく変更を加えました。**ARNI、SGLT2インヒビター、βブロッカー、MRA時代を踏まえ、その全てを初めから組み入れることといたしました。STRONG-HF研究では、研究を開始した時期にはSGLT2インヒビターのデータがなく、心不全治療薬としての承認が下りていなかったため、研究の中には入っていませんでした。そこで今回はこの4つの軸を中心に組み立てることにいたしました。
また、今回はACE阻害薬からの変更はしないというような方針といたしました。**これは、ACE阻害薬からARNIに変更する場合、36時間以上の休薬が必要であるため、煩雑になる可能性がありました。そこで今回は休薬の必要がないARBからの変更に限定させていただきました。
他の主な変更点に関してですが、それはNT-proBNPになります。**STRONG-HFはスクリーニング時に2,500以上、ランダム化の時には1,500以上、かつスクリーニング時より10%以上低下しているということが必要です。これは鬱血が残存していることを保証するためです。ただ、やはり入院中に2ポイント測定しなければならないという手間がありましたので、STRONG-HF-JAPANにおきましては、スクリーニング時の採血は省き、GDMT開始時に1,500以上あるということのみを組み入れ、それを基準にいたしました。
また、当然ではありますが、各薬剤の最大投与量は欧米とは全く異なります。**例えばβブロッカーでいいますと、カルベジロールの最大投与量は20mgになりますが、STRONG-HF本編では100mgになります。そこで、各薬剤の日本の実状に合わせて最大投与量を変更いたしました。
急性心不全患者に対して最大耐用量にGDMTを最適化する際の課題は何でしたか?
より早期にGDMTを行うことの課題に関しましては、やはりその認識にあるのだろうというふうに思います。**STRONG-HF-JAPANを計画した我々もそうですが、本当にこのプロトコールがうまくいくのかと、できるのかということでした。
これまでβブロッカーは鬱血がなくなってから開始し、少しずつ増やすということを諸先輩方から教わってきましたし、実際にこの研究を始める前は、実際にそのようにして治療を行ってきました。それを完全に破るわけですから、非常に抵抗がありました。ただ、STRONG-HFが海外でできているのであれば、我々日本人でもできるという信念がありましたので、つまり我々自身の認識を変えることが必要でした。
また、当然ではありますが、血圧、心拍数、腎機能、電解水異常の出現には注意が必要です。特にこのプロトコールを初めて実践する際には注意が必要だと思います。まず、この症例だと問題なくいけるという、そういった症例から始めるのが初めのうちは無難だと考えています。いきなり超高齢の慢性腎不全合併例、血圧低値例で開始してしまうと、非常に難しく感じてしまうかもしれません。
また、NT-proBNPをしっかりと活用することも重要だと考えています。NT-proBNPが経過とともに下がっていることを確認するということで、それが病態が改善していることを非常に把握しやすくなるため、それは非常に有用だと思います。経過中NT-proBNPが上昇するようであれば、鬱血の増悪や腎機能の増悪が察知できますし、NT-proBNPをうまく活用することが、薬剤の導入を安全に行うという観点からも非常に重要な点だというふうに思います。
実際にSTRONG-HF-JAPANでも、NT-proBNPをガイドに治療するプロトコールで薬剤の調整を行っておりますし、それが今のところ良好な結果につながっているというふうに考えています。
今回の臨床研究を通して得られた知見を基に、他のアジア太平洋(APAC)諸国の施設へSTRONG-HF試験のプロトコルを導入するために石原先生が推奨する上位3項目は何ですか?
STRONG-HF-JAPANの研究計画を立てる際に注意した事柄が、そのままAPACでも参考にしていただけるのではないかというふうに思います。**まず、医師の認識を変えることが重要だと思います。良い武器を持っていても使わなければ意味がありません。また、使用できる薬剤をそれぞれの地域で選択し、また投与量も実情に合った形で設定するということが重要だと思います。NT-proBNPを含めた採血の回数、検査のモダリティについても、その地域に合った形で設定する必要がありますし、外来のフォローアップの頻度も非常に重要な因子になるんだろうというふうに思います。